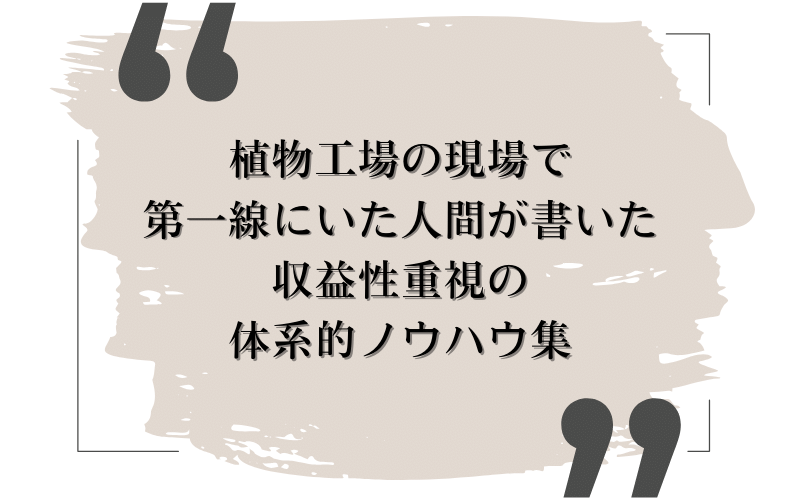

このページを開かれた、ということは、
あなたは植物工場や環境制御型農業に関連した職種の方で、
もっと収益を改善したり、生産を安定させたい、と思っていませんか?
もしそうなら、このコンテンツは役に立ちます。
みなさん、こんにちは。
著者の今村翔平と申します。
この本は、現場の第一線で10年以上働いてきた私が、
同じく現場の方へ、「植物工場の生産ノウハウを伝える」ために書きました。
実は、植物生理、植物工場のビジネス戦略、AI / IoT技術、といった情報は、少し探せば意外とカンタンに見つかります。
しかし、あえて本書は、最先端設備やシステムの話ではなく
「人が持つ、知識・スキル・テクニック」に何よりも重点を置いています。

いや、ちょっと待てよ。
「ところで、あなたが語るノウハウに価値はあるの?」そう思いますよね。
当然です。まずは私の自己紹介から始めますね。
私は2011年から植物工場業界に携わり、現場の第一線で経験を積みながら、これまで大小合わせて10箇所以上の植物工場運営に関わってきました。
その中には、日本トップクラスの生産規模を持つ工場がいくつも含まれます。
というのも私は、2015年から株式会社ファームシップという植物工場の会社に勤め、工場のサポート業務を8年間担当した経験があります。
具体的には、植物工場の立ち上げや再生をする仕事です。
一つの案件ごとに、2~3名のチーム体制で現地に1~2年間滞在し、自分達も現場に入りながらサポートや教育を行う仕事です。
引っ越しが多く、早いときは半年で引っ越したことも(笑)
サポートする工場の状況は様々。
ある時は、私以外の工場運営メンバーが全員、現場経験がない。という状況もありました。
そのような環境では、私たちには相応のノウハウと責任が求められます。
現場の最前線で指揮を取ることもあれば、同時に他のメンバーへの教育も欠かせません。
私はずっと、そのサポートチームのマネージャーをしていました。
つまり私は、
問題が山積する植物工場の立ち上げをこなしながら、人を教育し、現場を安定稼働するまで作り込めるレベル
のノウハウを持っているわけです。
特に、私より植物工場歴の長い人はいても、私より多数の現場を第一線で経験した人はいないのではないでしょうか。
そして本書は、この経験を持つ私だから書けるのです。
植物工場では、現場が違えば設備も違い、作業方法やルールも違います。
そうすると、前の現場で成功したやり方が、次も成功するとは限りませんよね?
そのような場合でも、現場に合わせて最適な方法を作り出してきた自負があります。現場の違いに左右されない「最適」を見つけるには、「本質」の考え方やノウハウが必要なのです。
この本の内容は、設備やシステムが違っても関係なく、収益性が高い現場を作るための、本質的なノウハウです。
つまり「本質」とは、正しく現場改善をするうえでの、基礎となる考え方やノウハウのことです。
しかも断片的ではなく、体系化された情報が理想的です。
実はこういう情報は、本やネット上からは意外と見つかりません。

植物工場の「運営方法」についての具体的な情報はない
「改善したい」と思ったら、情報を求めますよね?
私も業界に入った頃からずっと情報を求めてきましたが、本当に欲しい情報は、なかなか見つかりません。
確かに、植物工場に関連した情報はいくつもありますが…、私は頭を抱えていました。
「うーん、そうじゃない…」
「もっと…うちの工場でもすぐにマネできて、具体的なことが知りたい!」
みなさんも、そう思いませんか?
「とにかく、すぐ仕事を楽にしたいし、稼げるようにしたいんだ!」、と。
この本はそのために書きました。
とにかく、収益性、収益性、収益性。です。
私はずっと読みたくても読めなかったので、少しずつ自分なりに学び、経験し、蓄積したノウハウです。
収益改善の観点から、「本質的な考え方」や「具体的な行動」に、できる限りフォーカスした内容です。
植物生理、植物工場のビジネス戦略、AI / IoT技術などの話は、最小限か、ありません。それらは他の本やネット上から情報が得られるので。
みなさんなら、どんな情報が欲しいですか?
例えば、生産計画の立て方に関する情報は、どうでしょうか。
どのような手順で計画を立て、現場へ落とし込むのか。計画の決定に至る考え方、収益性の高い計画とする方法。
それ以外にも、収益性を高めるための、栽培管理、データ分析、作業工程など。
これらの具体的な方法論が書かれた本や文献は、意外と見つかりません。
しかし、もしかすると本書は、植物工場の仕事を長年続けている方にとっては、「知ってるよ」という部分もあるかもしれません。
でも考えてみてください。
そのノウハウを、若手社員へ伝授することは苦労するのでは?
「作業をどうやる?」ではなく、「作業のやり方を決める時、何を考える?」を教えなくてはいけません。その内容は多岐にわたります。
そのとき問題となるのは、植物工場の運営を体系的に解説している情報が無いことでしょう。
もし自社内で教育するなら、ノウハウを体系的に整理し、教育用のコンテンツを作成するコストを自社で負わなくてはなりません。
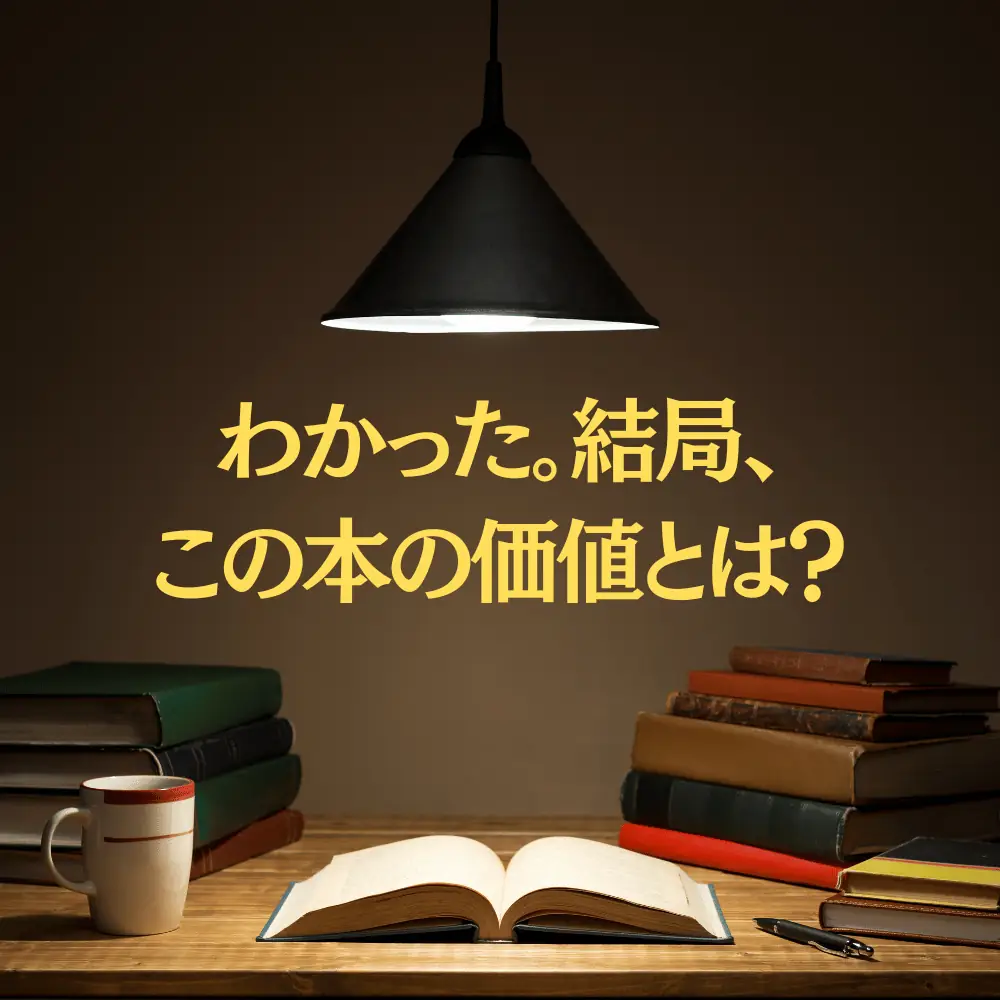
本書を読む価値
結論として、この本の価値は、
これまで組織ごとの一子相伝となっていた植物工場運営のノウハウが、
現場の第一線にいた人間によって、
収益性を高める観点から、
体系的に書かれていることです。
ただし前提としてこの本は、完全閉鎖型植物工場での栽培パネルを使用した水耕栽培システムを中心としています。私の経験とノウハウを書いているためです。
それでも全体では、トピック数が171個、文章量は20万文字以上となりました。
読者として想定しているのは、植物工場やその他の環境制御型農業に関連する職種の方です。
しかしこれだけの量があれば、他の施設栽培業界の方にとっても、役立つ情報が見つかるかもしれません。参考までに、本書の目次はすべて公開します。
最後に、価格ですが
同じようなものが世に中にないので、本書の価格には悩みました。
もともと暗黙知だったノウハウを体系化することは難しく、毎日10時間以上、約3ヶ月の期間を費やしました。
そもそも、このノウハウを編み出すまでに10年以上の月日を要しています。
長い年月をかけて経験し、検証を繰り返してきたのです。
そう考えると、決して安い金額ではお渡しできないと、ご理解いただけると思います。
とはいえ、早めに購入価格を回収できなくては価値がありません。
本書を読まれた方は、ぜひ内容を実践し、収益改善にチャレンジしてください。
読者のコスパまで考え出すと、さらに価格設定は難しいですが…。
それでも決めました。
中小規模の施設であっても、数ヶ月で投資回収を見込める価格として、
98,000円(税込)が妥当であると判断しました。
しかし、販売状況に応じて予告なく値上げする可能性がありますので、ご了承ください。
また、より多くの方の手に取っていただきたいので、発売からしばらくは
10%オフの88,200円(税込)で販売いたします。
それでは、本書がみなさんの工場のブレイクスルーになることを心から願っています。
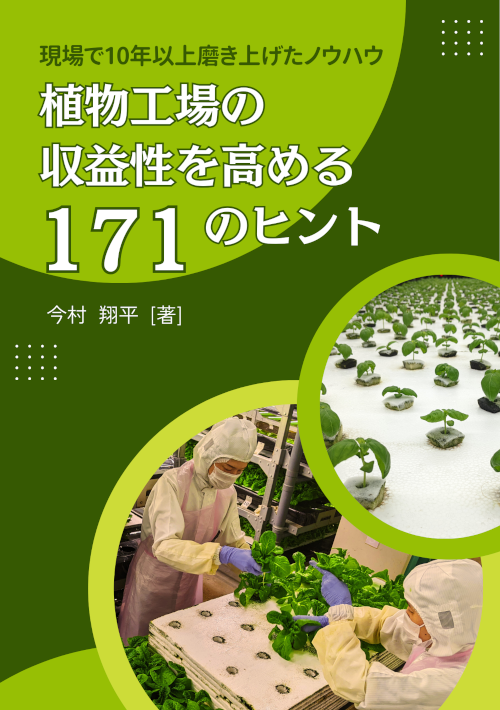
植物工場の収益性を高める171のヒント
現場で10年以上磨き上げたノウハウ
今村翔平(著)|形式:PDF
\期間限定10%オフ/
88200円(税込)98000円(税込)
2024年5月上旬発売予定。
以下のフォームより、メールアドレスを登録してお待ち下さい。
発売後にメールでお伝えします。
メールアドレス登録フォーム
植物工場の収益性を高める171のヒント 現場で10年以上磨き上げたノウハウ
はじめに:著者プロフィールと本書の紹介
目次
1 章 栽培環境の管理
🔴 1|基本を大切にする栽培管理は必ず報われる
🔴 2|生産性アップの第一歩は、光合成への理解
🔴 3|光合成をうまく操るコツは、栽培環境の「バランス」
🔴 4|もっとCO2と水に注目する
🔴 5|栽培管理の目的は「十分与える」ではなく、「絶対不足させない」こと
🔴 6|収量を増やす改善策で、コスパの高い要素はこの2つ
🔴 7|収量と品質のトレードオフ
🔴 8|栽培環境が作物に与える影響まとめ
🔴 9|作物の生育を最適化するシステム設定まとめ
🔷コラム|植物工場業界に入って感じたこと
2 章 温度
🔴 10|温度が高いほど植物の成長は早まるが、限界もある
🔴 12|温度が原因でチップバーンが起きるケース
🔴 13|成長段階に応じた温度設定によって生産性を高める
🔴 14|ベストな設定温度は、微調整を繰り返すことでのみ見つかる
🔴 15|季節の温度変化には早めに対処しておく
🔴 16|レタスは温度が引き金となって抽苔することがある
🔴 17|いくつかの代表的な地点に温度計を設置する
🔴 18|養液温度は気温と同じくらいならコントロール不要
🔴 19|急な温度変化によって、葉に結露を起こしてはいけない
🔴 20|ガッシリした良苗を作る手法:DIFを活用
🔴 21|DIFが使えない環境での代替手法「DROP」
🔷コラム|システム操作を忘れて帰宅、栽培室の気温がとんでもないことに…
3 章 湿度
🔴 22|生産者の役目は、蒸散の邪魔をしない湿度管理
🔴 23|高湿度の害:チップバーンの原因になる
🔴 24|高湿度の害:結露が起きる
🔴 25|局所的なチップバーンが出たら、高湿度が原因かも
🔴 26|除湿機とエアコンで湿度をコントロールする
🔴 27|高湿度で栽培するメリットと注意点
🔷コラム|常に湿度100%の環境で起きたこと
4 章 光
🔴 28|光合成での光の役割をおさらい
🔴 29|光が強すぎて障害が起こる理由のまとめ
🔴 30|生育不良は、光合成のエネルギー生産と消費のバランスが悪いときに起きる
🔴 31|光が強いかな…と思っても、まずは他の環境から確認すべき
🔴 32|作物にとって効果的な光の当て方
🔴 33|光反射板は取り付けておいて損はない
🔴 34|適切な照明器具の考え方
🔴 35|概日リズムを乱すと光合成効率が落ちる
🔴 36|生育障害が出ない限りは、照射時間を延ばすチャレンジを
🔴 37|弱光でも栽培するための戦略
🔴 38|長すぎる照明時間の弊害
🔴 39|植物工場のサニーレタスが赤くならない理由
🔴 40|明期or暗期の収穫タイミングによって、製品品質が変わる
🔷コラム|蛍光灯の交換で大失敗した話
5 章 養液循環と水
🔴 41|ECはおおよその肥料濃度しかわからないが、それで十分な理由
🔴 42|ECによって水分の吸収しやすさが決まる
🔴 43|ECは上限と下限を0.1の範囲内で管理する
🔴 44|昼夜でECを変えると、養液吸収を最適化できるかも
🔴 45|pHが高くなると、肥料成分が結晶化してしまう
🔴 46|pHの管理は、常に弱酸性を維持すること
🔴 47|養液のpHは、なぜ変化するのか
🔴 48|pH調整剤の使用は控えて、アンモニア態窒素の量でpHを調整する
🔴 49|ECやpH管理の他に、水耕設備に必要な機能
🔴 50|根が褐変する要因となる、クロラミンの発生
🔴 51|藻類を完全にコントロールしようとすべきでない理由
🔴 52|藻類の発生を抑える対策
🔴 53|溶存酸素濃度よりも養液の流れに目を向けるべき
🔴 54|栽培ベッドやタンク内にゴミが貯まるリスク
🔴 55|困った時に養液更新を選択できる安心感
🔴 56|全量の養液更新を無事に完了させるプロセス
🔴 57|効果が薄いうえにデメリットもある養液殺菌
🔴 58|「良い根とは、大きくて量が多いこと」という誤解
🔷コラム|涙と鼻水を垂れ流し、泣きながら掃除をした話
6 章 肥料の扱い
🔴 59|単肥を使った肥料作成の前提知識
🔴 60|処方が大まかで偏っていても、作物は問題なく育つ
🔴 61|微量元素は単肥ではなく、配合肥料を使うのが実用的
🔴 62|栽培環境に適した処方を見つける、たった1つの方法
🔴 63|状況変化に合わせて、柔軟に処方を適応させるべき
🔴 64|実用的な処方決定法
🔴 65|施肥設計シートを使った、具体的な計算手順
🔴 66|肥料計量ミスは絶対NG。必ず気づける仕組みにしておく
🔴 67|肥料撹拌を効率化する方法
🔴 68|濃縮原液をA,Bのタンクに分ける理由は「溶解度」
🔴 69|pHの影響で起こる沈殿にも注意する
🔴 70|栽培ベッドに貯まる茶色い砂は鉄が沈殿したもの
🔷コラム|施設や組織の立ち上げで、「これは大事だな」と思うこと
7 章 CO2と風
🔴 71|CO2は植物にとっての食料だと理解する
🔴 72|風が無いと光合成が進まない
🔴 73|CO2管理の基本スタンスは、「絶対に切らさないこと」
🔴 74|栽培室全体に作る空気流の役割
🔴 75|ベッド内に風を送ってもチップバーンがなくならない理由
🔴 76|CO2の供給は収量増加のコスパが良い
🔷コラム|私が新人へ「1000ppmのCO2は、家の中と同じくらい」と、いちいち説明する理由
8 章 栽培データ分析
🔴 77|栽培データは資産となり、栽培を成功に導く
🔴 78|収量はデータ分析を行うことで最大化する
🔴 79|コストを抑えて必要な収量データを得る方法
🔴 80|全パネルのデータ管理により栽培日数を追跡する
🔴 81|トリミングゴミ比率は生産性アップに欠かせない優秀な指標
🔴 82|作物の大きさを揃えることで収益性を最大化できる
🔴 83|収益性を維持するため、絶対に苗を不足させない
🔴 84|工場内で起こる異常やミスを、すぐさま察知する方法
🔴 85|何をもって「養液にトラブルが起きている」と判断するか
🔴 86|設備設定値の履歴を保存すれば、栽培の安定性が向上する
🔷コラム|システム化はどこまですべきか
9 章 生育障害
🔴 87|植物工場での栽培は、生育を早めることで起こる生育障害との戦い
🔴 88|最大の敵チップバーンと戦うには、発生原因の理解から
🔴 89|収穫前に急増するチップバーンへの対処
🔴 90|養液のカルシウム濃度を高めてもチップバーンが解決しない理由
🔴 91|チップバーンと戦いつつ生産性を最大化する「攻めては守る」戦略
🔴 92|照明器具に接触すると葉焼けが起こる
🔴 93|収量を上げたいなら徒長を起こさないこと
🔴 94|植物工場で徒長を防ぐための対策
🔴 95|根のダメージは地上部への悪影響が大きく、収量が激減する
🔴 96|水耕栽培でも連作障害はあり得るが、心配いらない理由
🔷コラム|チップバーンの本当の恐怖
10章 生産計画
🔴 97|収益を最大化するために、生産計画は綿密に立てる
🔴 98|生産と販売のミスマッチは、収益性を大きく下げる
🔴 99|植物工場に合わない品種は、決して選んではいけない
🔴100|生産性の高い栽培工程は、目標の収穫重量から決める
🔴101|生産性が最大となる栽培工程の決め方
🔴102|ベッド内の全パネルを同時収穫、毎日少しずつ、どちらが効率的?
🔴103|工場のキャパで生産できる最大量を栽培工程設計によって計算する
🔴104|稼働日数の考え方:毎日稼働が効率的とは限らない
🔴105|どのベッドを割り当てるかによって、作業量が大きく変わる
🔴106|栽培工程をスケジュールに落とし込み、いつ、どのような作業が発生するかを割り出す
🔴107|スケジュールに基づいて、必要な労働力を正確に管理する
🔴108|日ごとに必要な人員数を割り出して、人員の過不足を防ぐ
🔴109|生産計画を現場へ落とし込む方法は、「必要な情報を適切に」
🔷コラム|フル生産をしている工場が限界を超えるとき
11章 生産データ分析
🔴110|生産の成果を評価する:生産性の考え方
🔴111|正確な生産性分析のために、売上高と生産金額は別モノと考える
🔴112|収益性を常に追跡する
🔴113|品種ごとの原価分析によって、収益率の高い品目に集中すべき
🔴114|「1gあたりの売上・生産金額・製造原価」が最も信頼できる理由
🔴115|投入した費用が効率的に活用されているかを指標によって把握する
🔷コラム|「改善改善って言うけど、私たちが遅いってこと?」
12章 従業員の管理と教育
🔴116|必要な労働力を正確に把握し、過不足なく割り当てる
🔴117|人員をフル活用するために、デイリータスク表は不可欠
🔴118|「人の作業」が多いほど、教育の価値は高い
🔴119|整理・整頓などの取り組みは、なぜ失敗するのか
🔴120|「現場が忙しいから改善活動ができない」
🔴121|改善活動をしていると出現する、改善に反発する勢力を黙らせる
🔷コラム|作っても読んでもらえない作業標準書
13章 衛生管理
🔴122|植物工場の衛生管理は、エリア区分をベースとしている
🔴123|厳しいだけの非合理的な衛生ルールを作るのは失敗の元
🔴124|作業員個人の衛生ルール
🔴125|栽培エリアへの入室ルール
🔴126|長時間のゴシゴシ洗いはNG:合理的な手洗いルールを定める
🔴127|入社時の衛生研修はコスパが高い
🔴128|細菌管理のポイントは湿度コントロール
🔴129|作業中に手や備品を洗うべきケース
🔴130|植物工場の中であっても、実は普通にいる虫への対策
🔴131| 工場内での虫の繁殖は絶対に防ぐために、予防とモニタリングを実施する
🔷コラム|虫の大群が襲来した話
14章 発芽・育苗の工程と播種のポイント
🔴132|種子保管のポイント
🔴139|培地の選択とウレタンの含水
🔴140|播種作業
🔴141|発芽
🔴142|育苗期の管理によって、収量予測の精度を高める
🔴143|育苗
🔷コラム|苗運びの最中に起きた忘れられないハプニング
15章 生育工程と移植・定植のポイント
🔴144|苗の選別によって、大きくコスト削減できる
🔴145|移植
🔴147|定植で用意する予備苗は必要最低限だけ
🔴148|栽培ベッドの適切な維持管理
🔴149|あまり求められていない高付加価値化の経済合理性を考える
🔴150|有用成分が増えるメカニズム
🔴151|高付加価値化をするための具体的な方法
🔷コラム|後片付けをし忘れた栽培ベッドの悲劇
16章 収穫やトリミングのポイント
🔴152|収穫以降の作業は最も人件費がかかり、コスト削減の余地が大きい
🔴153|「他の人もいるから大丈夫」で起こる作業スピード低下を防ぐ
🔴154|少しずつでも早くなるよう教育しなければ、ずっと遅いまま
🔴155|収穫
🔴156|可能な限りの自動化と効率的な生産ラインの構築
🔴157|収穫後の野菜を濡らしてはいけない
🔴158|トリミングのルールは、厳しく見るポイントを定める
🔴159|正確なトリミングが生産性を高める
🔴160|作業中の「私語」が作業効率に与える影響
🔴161|野菜の保存性を決める要因
🔴162|葉菜類の収穫タイミングは暗期終盤が良いけど、明期終盤にもメリットあり
🔷コラム|工場内でのシャトルランで倒れそうになった話
17章 収穫後の作業全般
🔴163|収穫後の野菜の呼吸と冷蔵保存の重要性
🔴164|リーフレタスを包装して販売する理由
🔴165|収穫後工程の衛生レベルによるエリア分類と製品の移動制限
🔴166|包装前の計量
🔴167|包装
🔴168|検品と最終計量
🔴170|製品の在庫管理
🔷コラム|工場の立ち上げで経験した悪夢の2徹
18章 その他の作業
🔴171|清掃のポイントは、「ピカピカ」よりも「隅々まで」
🔴172|清掃する箇所は表を作って網羅する
🔴173|殺菌よりも、優先すべきは「乾燥」
🔴174|栽培パネルの汚れは、どこまで除去するのが合理的か
🔷コラム|記録は紙ベース?、それともデータベース?
19章 その他の管理業務
🔴175|漏れやミスがあってはならない点検業務にもチェック表を作る
🔴176|必要な消耗品を切らさないための管理方法
🔴177|トラブルを予測し、生産が停止した場合の対策を考えておく
🔴178|人間の脳の仕組み上、ヒューマンエラーは必ず発生するものだと認識する
🔴179|最強のエラー回避方法はダブルチェック(一人でもできる)
